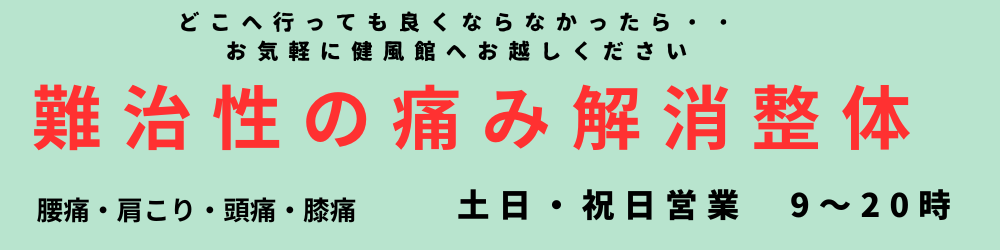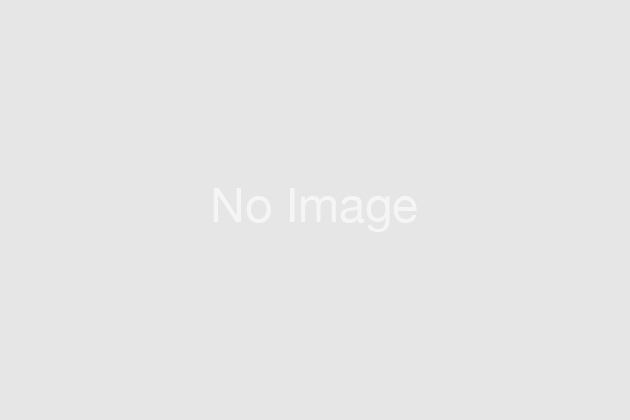ウォーキング
-
含胸抜背ウォーキング
【含胸抜背ウォーキング】 こんにちは、大内です。 『含胸抜背』 ってご存知ですか? 書いて字のごとく 「胸を含み、背中を抜く」 こ...
-
股関節ストレスフリーウォーキング術
【股関節ストレスフリーウォーキング術】 こんにちは、大内です。 腰痛や膝痛などが ある方に限らず 多くの人無意識に やってしまって...
-
歩く時腕は振らずに振られる
【歩く時腕は振らずに振られる】 こんにちは、大内です。 「ウォーキングの時に 腕はどういう風に振ったら良いですか?」 よくあるご質...
-
仕方なく出る前脚アニマルウォーク
【仕方なく出る前脚アニマルウォーク】 こんにちは、大内です。 私も毎日暇さえあれば やっているのがネコエクササイズ。 その場で行う...
-
脱筋力ウォーキング3つの意識とは?
【脱筋力ウォーキング3つの意識とは?】 こんにちは、大内です。 ウォーキングは 身体に良いということで 多くの人が行っている 代表...
-
足の着地は踵からですか?
【足の着地は踵からですか?】 こんにちは、大内です。 よくご質問いただくのが 「歩く時は足の着地は かかと着地ですか?」 これって...
-
ゆっくり動く習慣だけで腰痛改善
【ゆっくり動く習慣だけで腰痛改善】 こんにちは、大内です。 実は身体の調子が悪い人ほど 身体の動きが早いです。 と言うか ゆっくり...
-
杖の正しい使い方
【杖の正しい使い方】 こんにちは、大内です。 私の母は一昨年 お風呂場で尻もちをついて 左股関節の転子部の骨折。 そこから元々不具...
-
立った時の重心どこがベスト?
【立った時の重心どこがベスト?】 こんにちは、大内です。 当院でたま〜に いただくご質問が 「立った時はどこに重心を 掛ければ良い...
-
足の裏を感じるだけで腰痛改善
【足の裏を感じるだけで腰痛改善】 こんにちは、大内です。 ポイントはズバリ 『足の裏をセンサーとして使うこと』 多くの人が 良くや...