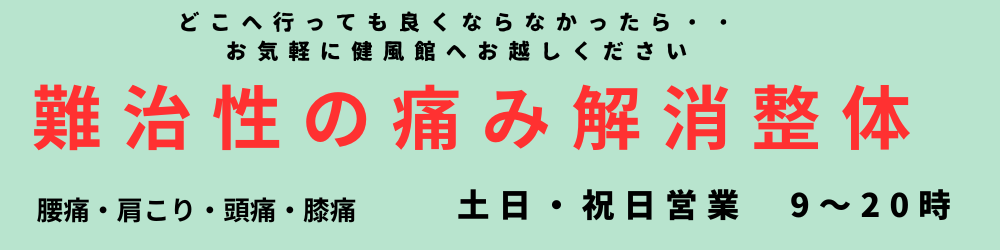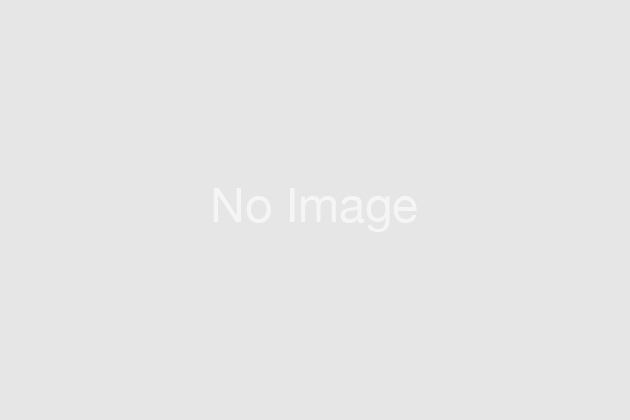介護の知恵
-
お祈りパワー
【お祈りパワー】 こんにちは大内です。 お祈りの力を あなたは信じますか? 「私は宗教は信じないんです!」 とか、 「お祈りで夢が...
-
腕を長く使うと身体はブレない
【腕を長く使うと身体はブレない】 こんにちは、大内です。 なんだか身体がフラついて 安定しないとか 立っていると疲れるなどと いう...
-
重たい物を楽に持つ方法
【重たい物を楽に持つ方法】 こんにちは、大内です。 今回の話をしっかり聞いて 実践いただければ 重たい物を 軽く楽に持てるように ...
-
モノにもたれ掛かって立つのはNG
【モノにもたれ掛かって立つのはNG】 こんにちは、大内です。 多く人がやってしまいがちなことが 何かモノにもたれ掛かりながら 立ち...
-
手すりの正しい使い方
【手すりの正しい使い方】 こんにちは、大内です。 コロナになってあまり 手すりや吊革などには 触れなくなった方は 多いかと思います...
-
杖の正しい使い方
【杖の正しい使い方】 こんにちは、大内です。 私の母は一昨年 お風呂場で尻もちをついて 左股関節の転子部の骨折。 そこから元々不具...
-
棒を使えばストレッチ度は3倍アップ
【棒を使えばストレッチ度は3倍アップ】 こんにちは、大内です。 昨年、お風呂場で尻もちを着いて 左股関節の転子部骨折、 そこから元...
-
良い姿勢は胸は張っても腹は引っ込める
【良い姿勢は胸は張っても腹は引っ込める】 こんにちは、大内です。 『良い姿勢』 とよく言われますが 姿勢が良いと言うのは 具体的に...
-
肩抱き落としは究極のコミュニケーション
【肩抱き落としは究極のコミュニケーション】 こんにちは、合気コミュニケーション整体師、大内です。 この『肩抱き落とし』は究極のコミ...
-
負けるが勝ちを体感できる方法
【負けるが勝ちを体感できる方法】 こんにちは、大内です。 『相手を感じる手合わせ』 というワークがあります。 実践動画はこちら↓↓...